体力をつける方法は?運動・食事・睡眠別に解説
世の中の健康常識は非常識!
本コラムは、一般的に語られている健康常識に、「分子栄養学」の祖である三石巌(みついし いわお)が唱えた「三石理論」の考え方を加えた記事です。
ぜひ、記事中に登場する【グリーンの四角の中】に記されたひとことポイントを、世の中の健康常識と比較してお楽しみください。
年齢を重ねるにつれ、運動する機会が減ってきたという人も多いでしょう。生活習慣は昔と大きく変わらないのに、「仕事の疲れがなかなか取れない」「風邪を引きやすくなった」など、基礎体力不足や身体の衰えを実感する人も少なくありません。
体力というものは、何もしなければ自然に低下し続けていきます。健康的な生活を長く送るためには、日頃から意識して体力づくりに取り組むことが重要です。
当記事では、体力をつけるために有効な方法を運動・食事・睡眠の3点から解説します。
目次
体力をつけるための方法(1)運動編
体力づくりをする前に、体力と持久力の違いについて理解しておきましょう。体力とは、日常生活や運動といった身体を使うすべての行動で必要とする、基本的な運動能力全般を指します。つまり、筋力・瞬発力・調整力・柔軟性に加え、持久力も体力の一部です。
持久力は、「筋持久力」と「心肺持久力」の2つに分けられます。筋持久力は、同じ負荷で同じ動作を何回行えるかという、筋肉の耐久力です。心肺持久力は、一定の運動を長時間続けられる心臓や肺の機能性を指します。
体力づくりには継続が大切です。筋肉は使わなければどんどん細く弱くなります。また、体力は加齢によって自然と低下する上、年齢を重ねるほどつけにくくなります。筋肉量の減少を食い止めて体力を向上させるためには、衰えのスピードを上回るレベルで刺激を与えられる運動習慣をつけることが大切です。
ここでは、体力をつけるために効果的な運動として、「ランニング」「スクワット」「筋トレ」のコツを簡単に紹介します。
トレーニング初心者の頃はきつく感じるかもしれませんが、続けていく内に身体が慣れ、徐々に運動効果を実感できるようになるでしょう。
ランニング
ランニングをはじめとした有酸素運動系トレーニングは、心肺持久力の向上が望めます。体力づくりのためにランニングを行う場合は、週2回1日2〜3km程度から始めるのがおすすめです。早く走る事よりも、正しい姿勢と呼吸を意識しましょう。
時間の目安は15〜20分程度、軽く汗をかく程度のスピードで走れれば理想的です。15〜20分のランニングもきつい場合は、30分程度のウォーキングから開始し、少しずつスピードを上げていきましょう。体力がついてきたと感じたら、週3回(もしくは1日おき)のペースに増やし、20〜30分ほど走ればさらなる体力アップが期待できます。
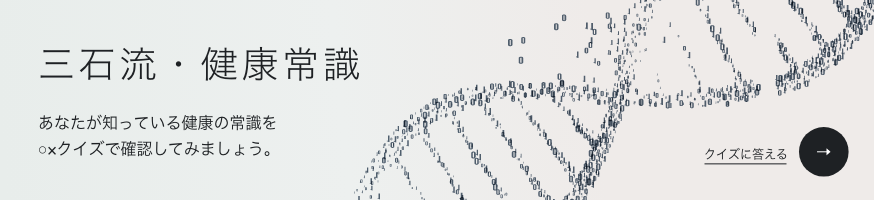
スクワット
スクワットはお尻や太ももを中心に、下半身の大きな筋肉を効率的に鍛えることで、体力の向上が見込める筋力トレーニングです。
下半身は、全身の筋肉量の60〜70%を占めると言われています。下半身を鍛えることで、歩く、座る、階段を上り下りする、重いものを持ち上げるといった、日常のさまざまな動作における疲労を感じにくくなります。自分自身の体力に合ったメニューを選び、体力及び下半身の筋力向上に努めましょう。
●初級
- ノーマル・スクワット
- ワイドスタンス・スクワット
- スプリット・スクワット
●中級
- ブルガリアン・スクワット
- シシー・スクワット
- ジャンピング・スクワット
筋トレ
有酸素運動を行うためには、筋持久力がなければ長時間の運動が困難になります。筋肉の持久力を高めるのにおすすめなのは、筋トレです。スクワット以外に下記のトレーニングメニューも、体力づくりにおすすめです。
- ヒップロール
- レッグシザーズ
- フロントブリッジ
- フロントレッグレイズ
- プッシュアップ
- バック・エクステンション
どれも20〜30回を1セットとし、インターバル30秒程度で2〜3セット行います。自分自身の体力に合わせて無理のない程度に実施しましょう。
三石は激しい運動は活性酸素を大量に発生させる原因となるため、勧めていませんでした。運動量が多ければ多いほど、身体にはたくさんの酸素を必要とします。体内で消費された酸素のうち一定数が活性酸素を生み出すため、酸素の消費量が多ければ多いほど活性酸素の発生量も増えてしまうということです。活性酸素は身体にとって必要ですが、大量に発生すると病気の原因となる厄介な物質です。そのため、激しい運動をする際には活性酸素対策が必要になります。
アイソメトリックスとは等尺収縮(アイソメトリック・コントラクション)を利用して、筋原繊維を増やす方法のことを言います。筋肉が、より多くの仕事をする能力をもつためには、筋繊維を太くする必要があります。筋繊維は、主に筋原繊維でつくられているため、筋原繊維が増えれば、筋繊維は太くなります。筋原繊維を増やすには、縮もうとする動きと、それを抑える力とを最大に対抗させ、この筋肉の緊張状態を6〜8秒間続けることが必要になります。
三石はお風呂やテーブル、トイレなど様々な場所でアイソメトリックスを実践していました。その中でお風呂で行っていた方法をご紹介します。お風呂に入った際に浴槽の側面を使い、腕、外太もも、内太ももの3カ所を実践していました。腕は浴槽の側面に両腕を広げるようにして力いっぱい押します。外太ももは足を立てた状態で広げ、腕と同じように浴槽の側面を押します。うち太ももは足同士を押し合います。それぞれの動きを6秒間続け、それぞれ3回ずつ繰り返していました。
体力をつけるための方法(2)食事編
体力をつけるためには、食事メニューのバランスと量にも気を配ることが重要です。体力をつけるための運動を継続しても、身体に入って来る材料が足りなければ、筋肉や血液を作り出すことができません。
人間の身体は、さまざまな栄養素が複雑に絡み合って構成されています。何か1つの栄養素だけを摂ればよいというわけではなく、身体の大きさや年齢に合わせて必要な分を必要なだけ摂ることが大切です。
何をどのくらい食べればよいか分からない場合は、厚生労働省(農林水産省)が公表している「食事バランスガイド」が参考になります。1日3食を心がけ、主食・主菜・副菜・汁物・乳製品・果物を毎食バランスよく食べましょう。
| 主食 | ご飯・パン・麺類など |
|---|---|
| 主菜 | 肉・魚・卵・大豆製品など |
| 副菜・汁物 | 野菜・海草・きのこなど |
| 乳製品・果物 | 牛乳・ヨーグルト・バナナ・柑橘類など |
食欲がないときはあっさりとした食材を食べるだけでなく、出汁や香辛料をきかせたり酸味を加えたりして味に変化を持たせると食べやすくなります。肉類は脂肪が少ない部位を選び、足りない分の脂質は牛乳などから摂取する方法も有効です。
また、下記の栄養素を意識的に摂るようにすると、効率的な体力づくりによいと言われています。
- タンパク質
- 鉄分
- ビタミンA・C・E
- ビタミンB群
食事だけで必要な栄養素がバランスよく摂取できないときは、プロテイン(タンパク質)やサプリメントも活用しましょう。
三石が考える、体力をつけるための栄養対策
体力の低下の原因として、体内の代謝がスムーズに行われないことが考えられます。加齢や食生活の乱れ、ストレス、睡眠不足などにより、細胞数が減少したり、代謝を司る酵素(良質タンパク)や補酵素(ビタミン、ミネラルなど)、エネルギー、酸素などの材料が不足することによって起こります。
代謝の際に必要なエネルギーは、糖質や脂質などを原料にビタミンB群・ビタミンC、コエンザイムQ10が補酵素となり細胞の中のミトコンドリアで作られます。 年齢と共に、ミトコンドリアの数やコエンザイムQ10の体内での合成量が減り、さらには動脈硬化などが進む事で血流の状態も悪くなり酸素不足になります。これによりエネルギーづくりの効率は必然的に悪くなることが考えられます。
栄養対策として代謝に必要な栄養素に不足が起こらないようにするために、良質タンパク、ビタミンB群・ビタミンC、コエンザイムQ10を摂取されることをおすすめします。また、代謝の際には必ず活性酸素という物質が発生しますが、ストレス・炎症・痛み・薬の摂取・飲酒・喫煙・大気汚染など、様々な要因により発生量が多くなります。活性酸素対策にはビタミンC、ビタミンE、植物ポリフェノールなどの抗酸化成分を不足のないように摂取することもおすすめです。
体力をつけるための方法(3)睡眠編
効率よく体力をつけたいのであれば、日々の睡眠時間を十分に確保することも重要です。脳や肉体は、睡眠を取ることで疲労回復が進み、同時に成長ホルモンなどの内分泌機能活発化によって、代謝の促進や筋肉の成長につながります。睡眠不足になると、疲労の蓄積や自律神経の乱れを招くため、体力をつけるどころか日々のパフォーマンス低下を招く恐れがあります。
適切な睡眠時間は、個人差が大きく年齢によっても変化しますが、一般的な成人の理想的な睡眠時間は、6〜8時間程度です。目覚ましがなくても自然に目が覚めて、かつ日中に眠気で困らない程度の時間を目安にするとよいでしょう。
下記は、体力づくりによいとされる良質な睡眠を取るためのコツです。
- 食事は就寝の3時間程度前には終わらせる
- 就寝2~3時間前に40℃前後のお風呂に15〜30分程度浸かる
- 就寝30分〜1時間前から間接照明などに切り替える
- 就寝前はパソコンやスマホをいじらない
- 就寝中は明かりを消す
- アイマスクや耳栓を利用する
また、毎日同じ時間に睡眠と食事を取る習慣をつけて生活リズムを整えることも、良質な睡眠によいと言われています。起床したら太陽の光を浴び、栄養バランスがよくタンパク質が十分に含まれた朝食を摂るように心がけましょう。
睡眠のリズムを正常に保つためには、身体の機能を正常化する必要があります。そのためには、良質タンパク、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンE、コエンザイムQ10、ミネラルなどの代謝レベルの向上に必要な栄養素を不足のないように摂取することが大切です。
入眠物質の1つとして知られるメラトニンは、アミノ酸のトリプトファンからセロトニンを経て合成されます。
トリプトファンは、体内では合成できないため、トリプトファンを多く含む乳製品(牛乳・チーズなど)や大豆製品、肉、魚などの食品の摂取によって、安定したメラトニン合成を促すことにつながります。その他、合成には共同因子としてビタミンB6、ナイアシン、マグネシウムなどが必要です。
自律神経は、交感神経と副交感神経の二つに分かれており、身体活動が活発になる時間(朝・昼)は交感神経が優位になり、副交感神経は活動の落ちる時間(夜)に優位になり、睡眠と覚醒のリズムをコントロールしています。しかし、2つの神経のバランスが崩れると、体内時計が狂ってしまい、夜になっても眠れない状態になります。
神経の働きを正常に維持していくには、各種神経伝達物質が過不足なく作られる条件を整えていくことが大切です。そのためには、アミノ酸(トリプトファン、チロシンなど)、ビタミンB群(特にB6、B12)、ビタミンC、カルシウム、マグネシウム、レシチンなどの栄養素の摂取を充分に行っていく必要があります。
自律神経は、ストレスや環境の変化などによっても影響があります。ストレスに対応していくためには、良質タンパク、ビタミンC、ビタミンEなどの抗ストレスホルモンの材料となる栄養素の摂取が必要です。またストレス時には、活性酸素の発生量が多くなり、身体に負担を与えます。活性酸素対策には、ビタミンC、ビタミンE、植物ポリフェノールなどの抗酸化成分が必要です。
体力だけでなく免疫力(抵抗力)をつけることも大切!
体力をつけたいと考えるのであれば、同時に免疫力(身体抵抗力)を高めることも大切となります。免疫力とは、菌やウイルスなどの病原体から、身体を守る力のことです。免疫力が低くなると、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかったり、症状が長引いたりします。また、がんの発症抑制にも、免疫力は大きく関係していると言われています。病気のリスクを下げ、健康な毎日を送るためには免疫力を高める努力が大切です。
免疫力を高めるには、適度な運動・バランスのよい食事・十分な睡眠をベースに、プラスアルファとして以下のことも意識するとよいでしょう。
●日光浴をする
日光に含まれるUV-Bを浴びると、免疫力を高める作用のあるビタミンDが体内で合成されます。夏であれば10分程度、他の季節は太陽光の強さによって適宜調整しましょう。ただし、日光は浴びすぎても悪影響が出やすい点と、UV-Bはガラスをほとんど透過しない点にも注意が必要です。
●腸内環境を改善する
腸は全身の免疫細胞の約70%が集まっており、腸内環境が悪化すると免疫力も低下します。バランスのよい食事を前提として、食物繊維や乳酸菌、ビフィズス菌を積極的に摂り、腸内の善玉菌を増やしましょう。
●身体を温める
体温が下がると、免疫力も低下します。40℃前後のお湯に10分程度浸かる・自律神経を整える・ストレスを緩和する・温かい飲み物や食べ物を摂取するなどの方法で、身体を冷えから守りましょう。
●たくさん笑う
笑うことで、がん細胞やウイルスなどを退治してくれるNK細胞が活性化します。また、血行を促進して新陳代謝を活発にしたり、自律神経を整えたりする効果も期待できます。作り笑いでも本当に笑ったときと同等の効果が期待できるため、習慣化するとよいでしょう。
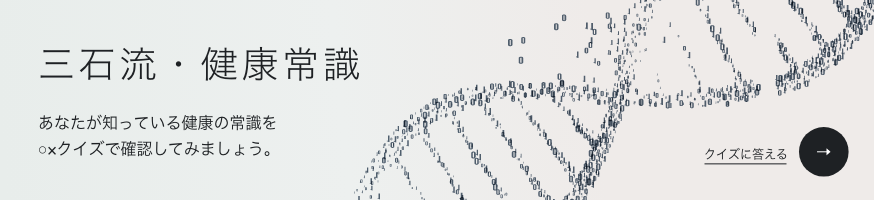
まとめ
体力をつけるためには、適度な運動を継続しつつ、栄養バランスのよい食事と十分な睡眠を確保することがポイントです。同時に免疫力を高めることも重要であり、これらを意識した生活習慣を送ることで、効率的な体力アップを見込めます。体力をつけて健康的な身体を維持したいのであれば、まずは日々の生活スタイルから見直しましょう。
なお、今回紹介した内容はあくまでも一般的に言われている方法であり、体質や環境によってはデメリットになる人もいます。効率的・効果的に体力をつけたいのであれば、医師などの専門家に相談してみることも有効な手段の1つです。





